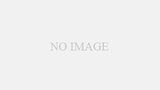今回は長期視点での大底圏にあるような銘柄の特徴について解説します。

現在のチャートでは三井科学の月足チャートを見ていますが、月足とはローソク足1本分が1ヶ月に相当します。一般的に株価の動きは長期で見た場合、大きなうねりを付けることが多いです。その際に、過去に下げ止まったポイントや株価水準が低くなっているかどうかを確認することが重要です。
特に長期の大底圏にある銭柄は株価水準も低いため、中長期視点では値上がりの機会が大きくなるといえます。この判断をする上で重要なのが移動平均線の位置です。移動平均線と株価の乖離の関係を見ることで、長期的に大底圏にあるかどうかの判断がしやすくなります。たとえばこのチャートパターンのように、60ヶ月線の下に位置する-30%や-50%のラインに株価が近づいていると、大底圏にある可能性が高まります。
このような大底圏の銘柄は一旦値上がりをすると、一般的に大きく高値を目指しやすいという特徴があります。このような視点を持ちながら大底から立ち上がりの期待ができる銘柄を選ぶことが重要です。今回はこのようなポイントを動画で解説しておりますので、ぜひご覧ください。