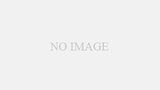今回は、市場が急落した場面でも有効に使えるオシレーター指標「RSI」について解説します。

RSIは株価の値上がり幅と値下がり幅のバランスを見ることで、相場の過熱感や反転の兆しを判断するために用いられる指標です。RSIは0%から100%の間で推移し、一般的には30%以下で「売られすぎ」、70%以上で「買われすぎ」と判断されます。現在のチャート上では、14日間のRSIを表示し、30以下と70以上のラインに色をつけ、さらに赤線で10日平均線を加えています。このチャートパターンは「株の達人」の標準条件で簡単に表示できます。
RSIの基本的な見方として、30を下回ると売られすぎで下げ止まりの可能性が高まりますが、30を下回ったからといってすぐに反発するわけではありません。重要なのは、RSIがその後上昇し、10日平均線とクロスするタイミングや、再び30を上回ってきたポイントを確認することです。これらは実際に買いシグナルの一つとされており、相場の底打ちから立ち上がる場面を捉えるのに役立ちます。
RSIは株価の動きに対して細かく上下する特性があり、特に「50」のラインはトレンドの分岐点とされます。50を上回ると値上がり幅が大きくなっており、相場に強さが出ていることを示します。つまり、30を下から上に抜けて、さらに50を上回るようであれば、上昇トレンドが本格化してきたと判断することができ、ポジションを継続する根拠にもなります。RCIと違ってRSIは傾きでの判断が難しいため、値の変化や平均線との交差を中心に見るべきです。
また、RSIが70以上となって「買われすぎ」となったとしても、すぐに相場が反転するとは限りません。実際、70を超えてからもしばらく上昇が続くことはよくあります。高値圏ではRSIが下がり始め、10日平均線を割り込むタイミングで頭打ち感が出てくるため、そのタイミングもチェックポイントの一つです。
さらに、相場が動いていない持ち合いの局面では、RSIが50付近で細かく上下する特徴があります。これは売りと買いが拮抗している証拠であり、トレンドがない状況であると判断できます。RSIはこうした持ち合い相場でも有効に機能するというのが大きな特長です。
今回はこのようなRSIの使い方を相場判断のポイントを動画で解説していますので、ぜひご覧ください。